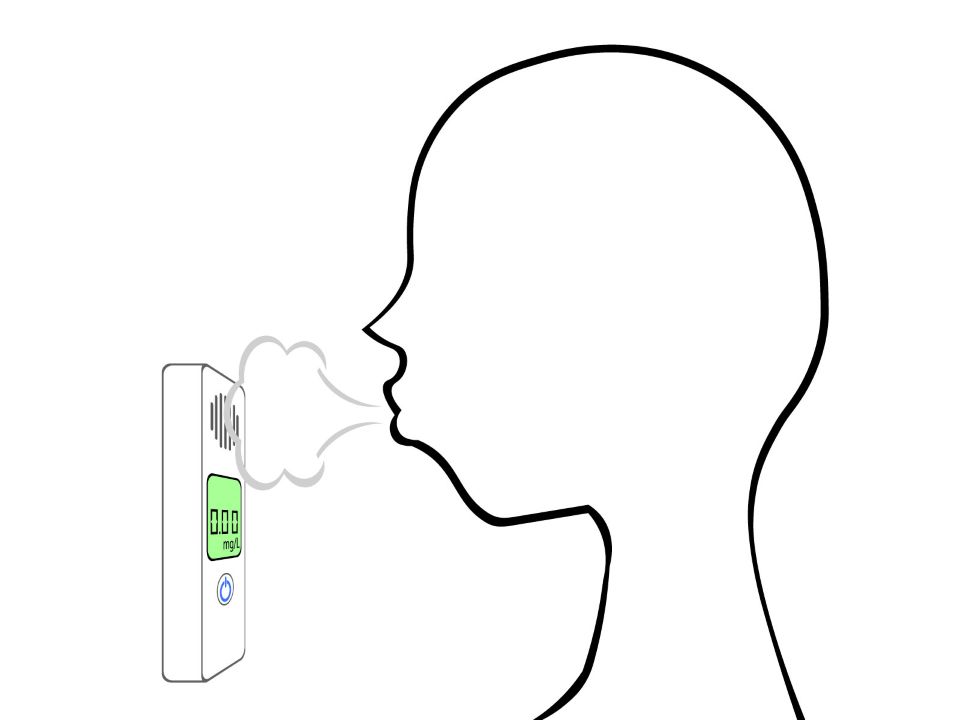私の運転士生活(1988年~2014年)の晩年に導入されたアルコールチェック。
動力車操縦者運転免許の取消等の基準というものが2010年3月に出され、酒気を帯びた状態で列車を操縦した者は免許の取り消しとなることが明記されました。
人様の命を預かって電車という大きな機械を操作しているのですから、酒に酔った状態での操業なんて考えられません。
さらに2019年10月4日、鉄道に関する技術上の基準を定める省令等の解釈基準、動力車操縦者運転免許の取消等の基準などを改正し、現在は以下のように定められています。
(1) 事業者に対し、運転士への酒気帯びの確認について以下の事項等を規定
・ 仕業前後に酒気帯びの有無を確認
・ 酒気帯びの有無の確認はアルコール検知器(ストロー式、マウスピース式)の使用に加え、目視等により行う
(仕業前の確認以降、事業者の管理の下にある場合は、仕業後のアルコール検知器を用いた検査を省略可)・ 仕業前に酒気を帯びた状態が確認された場合には当該係員の乗務禁止
・ 次に掲げる事項の記録・保存
確認を行った者及び確認を受けた者の氏名、確認の日時・方法、酒気帯びの有無(2) 運転士に対し、酒気を帯びた状態で列車等を操縦した場合の行政処分(運転免許の取消)適用上の目安を設定
・身体に血液0.2g/ℓ以上又は呼気0.09mg/ℓ以上のアルコール濃度を保有している場合
・上記にかかわらず、飲酒の影響により、反応速度の遅延など列車等の正常な操縦ができないおそれがある場合
私が乗務していたころは記録に残しておくと言うことがなく、乗務前のチェックでアルコールが検出されなければOKという運用でした。
酒気を帯びてないことをアルコール検知器を使って、出勤管理の助役の前で証明しなければなりません。
アルコールが検出されたらその日は乗務停止で、こんこんとお説教を聞いて反省文を書かされます。
私はまったくお酒を飲まない(体質的に飲めない、飲むと全身に発疹〈じんましんみたいな〉が出ます)のですが、そう言ったことは関係なく乗務前のアルコールチェックは必須です。
自身で飲んでいないことはわかりきっているから、アルコール検知器に息を吹きかけたところで何の心配もないですしね。
それでもマウスウォッシュで口をすすいだ時やガムやキャディーを口に入れていたなど、飲んでいなくても検知されることがあります。
パンやチョコパイを食べた後もそうですが、運転にはまず影響がないはずものであっても検知器での検査で乗務不可な数値が検出されることもあります。
軽く水で口をすすげばアルコールは検知されなくなるのですが、お酒を飲んだ場合は体内から吐き出される息にアルコールが含まれていますから、口をすすいだ程度では何回計測しても検知されますので、特に問題にはなりません。
でも2025年5月21日の養老鉄道の発表では、酒を飲めないとの申告だけで数年間にわたりアルコールチェックをせずに運転させていた。
ベテランの運転士で監督者(助役)たちが指摘しづらく、さらに検査していないのに検出されなかったとウソの数値を記入していたといいますし、監督者15人中11人が当該運転士に対するアルコール検査を黙認でパスさせていたという。
私がいた会社もたいがいなモノでしたが、さすがにアルコールチェックに関しては運転士・車掌の全員を対象に乗務前にチェックを行っていました。
私のように体質的に飲めないと会社側もわかっていても関係なく全員検査していましたが、まさか令和の時代に入って昭和のの頃のような検査体制がまかり通っていたとは……。
養老鉄道の場合は匿名で社員のだれかが運輸局へ相談したから発覚しましたが、相談しなかったらその運転士が退職するまでずっと……。
昭和の頃は酔った状態で電車を運転する人も正直多かった。
国鉄では飲酒によってかなり大きな事故も起こしていますしね。
ついさっきまで飲んでいただろうと言う状態で出勤してくる乗務員もいたし、泊りの仮眠時間中に飲んでいる人も本当に多かった。
所属する乗務区以外で仮眠をとる仕業(区外泊)の時なんて、乗務員室に酒と肴(つまみ アテ)を積んでその日最後の乗務を行うなんてことも行っていたし、冬場に古い電車が回って来た時なんて、乗務員室のシーズ線ヒーターの金属のカバーの上に日本酒の入った瓶を置いて、いい感じの熱燗にして仮眠中に飲むなんて人もいました。
でもこういうことは昭和の時代までのはず。
今は当然のようにアルコール検知を行い、飲酒した乗務員を排除するのがふつうです。
なのにアルコールチェック自体をパスする運転士と黙認する監督職がいるって、ホントに考えられません。
まさか他の鉄道社局も同じようなことはしていませんよね?